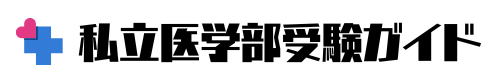私立医学部受験ガイドの運営者は、子どもが私立医学部に実際に通っている親です。子どもの医学部受験をきっかけに医学部の情報収集を開始し、医学部情報を発信しています。
医学部受験に関する情報は、インターネット上には多くあふれています。ただ子どもが医学部受験をするにあたり様々な情報を探すようになった結果、一般向けに発信されている情報には、いくつかの問題があったことが、サイト開設のきっかけとなりました。
特にその問題は、偏差値で見て中堅~下位に位置する私立医学部を受験しようとした場合に大きくなります。
医学部受験情報の問題点
1.国立や上位層向けの情報が多い
医学部受験に関する情報は、YouTubeでも発信者が多数存在し、インターネット上では数多くあふれています。
ただその多くが、国公立医学部や、私立の中でもいわゆる御三家など、上位の学校を中心としたものです。
例えばYouTubeであれば、閲覧数を稼がないといけないため、どうしても知名度がある学校や、一般にもうけそうな内容で配信をする傾向があります。
そのため、医学部受験層の中ではある程度需要があるものの、一般向けには需要が低いと見られる、中堅~下位の私立医学部に関する情報は少なくなる、と言う傾向があります。
実際に子どもの受験の時には、この情報の少なさによる思い込みもあり、選択肢が狭められていたという現実もありました。
ただオープンキャンパスなどで様々な学校の情報を得てみると、ネット上の一般的な情報だけでは得られない知識を得ることができ、受験できる学校の選択肢が広がりました。
2.踏み込んだ情報は少なく、勉強法に偏る
インターネット上では医学部受験に関する多くの情報が配信されているものの、その多くはいわゆる一般的な内容であり、「踏み込んだ内容」が実際には少ないです。
また勉強法に関する情報や、受験に関する情報は多くあるものの、例えば私立医学部の「学費」や「奨学金」といった、実際に通いたい人が知りたいような情報は、詳しくは紹介されてはいません。
こういった踏み込んだ情報の少なさが、私立医学部受験の壁を厚く・大きくしているとも言えます。
3.発信者自身が上位校出身
これは特にYouTubeの場合ですが、医学部受験情報を発信するチャンネルは複数あるものの、その発信者の多くは、国公立や私立の上位校出身者です。特に医学部専門塾の場合は、その傾向が強いです。
YouTubeで情報を発信する場合は、「誰」が発信するかということも重要なため、上位の学校出身であるいう学歴を重視することは、仕方が無いこととは言えます。
もちろん、塾や予備校のチャンネルに出ている発信者の場合は、その教え子には中堅~下位私立医学部の受験者も多いと思われます。ただ発信者自身が上位校出身のため、どうしても発信内容は、自身の経験に引っ張られてしまいます。
例えば、私立医学部で受け取ることができる「奨学金」の情報などは、専門家としてYouTubeチャンネルで発信しているにもかかわらず、人聞きのような表面的な情報しか発信していない人もいます。
発信者のバックグラウンドというのは、どうしてもその発信内容に影響してしまうため、結果として中堅~下位私立医学部の情報については、内容が薄くなってしまっています。
4.専門家なのに「それだけ?」といった情報も
これもYouTubeチャンネルに多いと思われる傾向なのですが、専門家として詳しく解説しますとして発信しているにもかかわらず、「それだけ?」といった内容のものも少なくないのです。
例えば、「今年狙い目の医学部」といった情報が発信されていた場合、誰もが知っている内容じゃない?といったものや、それは一部の上位層だけの話では?といった内容のものも多く含まれているのです。
もちろんそういった「表面的な内容」であっても、YouTubeチャンネルという、不特定多数に向けた情報としては閲覧数を集めることが可能なのでしょう。
ただ中堅ぐらいの私立医学部を受ける人にとっては、そういう表面的な内容ではなく、「今年の試験日程」「近年の受験傾向」「模試の動向」などを分析した上で、中堅~下位の医学部ではどこか狙い目が無いのか?といった、踏み込んだ情報を知りたいはずです。
そういった「本当の知りたい」要望に応えてくれる情報は、多くはありません。
5.詳細な情報は内部だけで共有
医学部専門予備校の中には、積極的に情報発信をしている予備校もあるものの、一般向けに発信されている情報は、限定的なものに限られます。
例えば実際に合格した生徒から寄せられた情報は、一部は合格実績などで公開されているものの、その大部分は一般には公開されません。
これはインターネット上での情報発信だけでなく、セミナーのようなある程度限られた場での情報発信も同じで、一般向けの情報公開では、どうしても発信できる範囲が限られてしまいます。
特に特定の学校に関する情報発信の場合は、ポジティブな場合はまだしも、ネガティブな情報となると、どうしても不特定多数向けには発信できません。
ネット上には多くの情報があふれるものの、結局は先にも指摘したように踏み込んだ内容ではなく、どれも同じような表面的な情報が多くなってしまいます。
ある程度仕方が無いことではあるのですが、本当に知りたい詳細な情報は、塾や予備校の内部だけで共有されており、あまり表には出てこないのです。
6. 医学部専門予備校の実際の合格実績は私立が中心
これは問題点というわけでは無いのですが、一部の大手を除けば、医学部専門予備校の実際の合格実績は私立医学部が中心です。
YouTubeなどでは、国公立や上位校の情報を積極的に発信しているような塾や予備校の場合でも、実際にその合格実績は、私立医学部、それも中堅~下位私立が中心なのです。
医学部専門予備校の多くは、一般的な予備校に比べて学費が高くなる傾向があり、結果として、私立へ通わせることができる家庭の子息が通うことになるので、当然と言えば当然の結果です。
また国公立に合格出来る学力がある層は、駿台や河合塾、東進といった大手に通うことが多いです。こういった層は結局どこに通っても合格出来るため、高額な学費が必要な医学部専門予備校に通う層にはなりづらいのです。
先にも書いたようにこれは問題点では無いのですが、結局中堅~下位私立へ多くの合格者を送り出しているにもかかわらず、その情報は発信されていない、という状況があるのです。
情報不足は選択肢を狭める
現在の医学部受験は「情報戦」の側面も強くなっています。
受験校選択に当たっては、他の学部のように偏差値だけで判別すると、失敗の原因となってしまいます。
勉強法や毎年変わる入試制度はもちろん、私立医学部では、学校毎の奨学金や留学の支援といった金銭面のサポートも重要な情報となります。
公表されている学費や偏差値だけを判断材料に検討すると、最初から選択肢に入れることもせず、自ら進路を狭めてしまいます。
私の子供の場合は、1浪で私立医学部に合格しましたが、現役時は情報不足と思い込みから選択肢を自ら狭めていました。
もちろん情報収集はある程度していたはずなのですが、上記で挙げた問題点から、一部の学校に偏った情報収集になっていたのも事実です。
私立医学部の受験においては、一定の学費(例えば、6年間で3,000万円以下など)で線引きをしているという人は少なくなく、線引きした学費以上の学校については、情報収集をしても無駄として調べもしない人は珍しくありません。
ただ学費は、「奨学金」や「ローン」など、医学部ならではの対処法が実際にはあります。
私立医学部に通う方が金銭面でメリットになることも
「学費の高さ」だけを理由に私立医学部を選択肢から外した結果、多浪をしてしまうと、金銭面でも損をしてしまうことはあります。
医者の平均年収は、勤務医でも約1,500万円と言われます。つまり1年医者になることが遅れれば、1,500万円損しているとも言えます。
6年間の学費が3,000万円の私立であったとしても、2年間の浪人で達してしまう額です。
さらに浪人を1年するためには、大手の予備校であったとしても100万円単位のお金が必要になります。
結果として、難しい国公立に挑戦し続けるのでは無く、早く私立の医学部に入学してしまった方が、金銭面でもメリットになることは、普通にあり得ることです。
もちろん、医学部に入学したからと言ってすぐに収入が発生するわけでは無く、また年収も保証されたものではありません。
医学部6年間に通うための高額な学費を払うことが難しい、という現実はあります。
ただその高額な学費をカバーするための方法は、実は色々存在していたりもするのです。
その情報を知った上で検討するのと、知らずに最初から目にも入れないのでは、状況はかなり変わると言えるでしょう。
経験ではなく調査した情報から発信
私立医学部受験ガイドは、前述した情報不足や、思い込みによる情報収集の遅れから、受験生の選択肢を狭めてしまうという問題を少しでも解決したい、との思いから立ち上げたサイトです。
筆者の子どもも私立医学部受験を経験しているものの、私立医学部受験ガイドでの情報発信にあたっては、自らの経験よりも、様々な調査により入手した情報を元にした発信を心がけています。
個人的な経験はもちろん貴重な情報源ではありますが、あくまでn=1にしか過ぎず、そこに重きを置いてしまうとどうしても偏った情報となってしまいます。
それよりも、多数の情報源から集められた資料に重きを置いて発信することで、より正確で有用な情報を提供できます。
もちろん、実際に医学部に子どもが通う親としての立場でしか分からない情報もあるため、それも加味して、他にはない唯一無二の情報サイトとしています。